■判型AB判 ■ページ数128ページ ・あこがれの美しい文字 ・思いを伝える短文を書こう ・ここぞで役立つ暮らしの書 ・集中力で美文字へ近づく ・模写で思いを読み解く ・心をつかむ手紙を書こう ・濃淡でも文字力アップ ・わたしらしさを文字力で
A4判 30ページ 技法DVD付 《主な内容》 墨を美術教育へ生かすためのテキスト。 墨を使った作品制作や、刷毛・和紙を利用した表現、実践学習の様子などが日本語と英語で紹介されています。
著者:日貿出版社 サブタイトル/書のスタイルブック ジャンル:書道 体裁/B5変・111頁 かな書を得意とする10人の実力派書家の競演で楽しむ、流麗で雅な百人一首の世界。小作品から大作まで様々なスタイルで表現された全100首に、歌の意味と作者についての解説、書家によるコメントを添えました。書美を追究する最先端の表現であると同時に平明かつ美しく、密度の濃いお手本集となっています。 ●目次 はじめに/かな書の基本/百人一首を書く 1~100/『百人一首』の世界/揮毫者一覧 揮毫:岩井秀樹、大石三世子、下谷洋子、高木厚人、田頭一舟、原奈緒美、日比野実、三宅相舟、山根亙舟、吉田久実子
著者:前田 篤信 ジャンル:書道 体裁/B5・192頁 省庁に長年在任し、表彰状・祝辞・辞令など数万枚を揮毫してきた著者。その経験をふまえ、誰にでも書ける表彰状・賞状のノウハウを詳しく教えます。1987年初版、豊富な実例と文例、格調高い毛筆文字、具体的な書き方が好評のロングセラーが、新元号「令和」に一部の作例で対応して装い新たに登場です! [主な内容] 1 賞状の書き方 用具類、姿勢・執筆法・腕法 書く時の要領、割り付けの要領 2 賞状のための細楷の技法 基本点画の書き方、字形の整え方、ひらがなの書き方 3 賞状の作例 表彰状・賞状・感謝状・その他 4 賞状の文例 表彰状・賞状・感謝状・その他 5 祝辞の書き方 胸章(リボン)の書き方、式次第の書き方 公文書の手引 ●まえだ・とくしん 大正14年香川県高松市に生れる。松本芳翠、吉田栖堂先生に師事。昭和22年農林省に入省。統計情報組織を経て、昭和38年農林大臣官房秘書課係長。同48年同課課長補佐。同59年定年。その間、20有余年に亘り、本務のかたわら特命事項として、大臣名の辞令、賞状、祝辞等数万枚を揮毫する。書道玄海社常任理事、(財)日本書道美術館参与を歴任、若葉書道会を主宰した。平成2年4月死去。
著者:根岸 嘉一郎 サブタイトル/現代感覚で楽しむ ジャンル:水墨技法B 体裁/A4変・103頁 「基本的な用具で多様な表現をすること」「様々な画材や特殊技法を用いながらも、シンプルで自然な表現をすること」。双方に目を向けた二部構成で学ぶ、水墨画創作のための新しい手引き。多くの愛好家を指導するとともに、これからの墨の表現を追究し続ける著者が、多彩な画材と技法を、実際の作品で具体的かつ詳細に解説しています。 主な内容 1章:基本技法で描く水墨画 ・墨の力、水の力/描法解説:天使の梯子 ・墨でたどる故郷:松川橋/田舎道/小布施の蔵/穂高連峰/上高地/浄光寺/北信五岳/二段滝/早春/渓流/雲龍図 ・花と鳥たち:芙蓉/菖蒲/シクラメン/鳶/土筆と雀/桃と菜の花/竹に雀/小春日和/水琴 2章:表現の幅が広がる各種画材と技法 ・各種画材と技法 ・ニカワ(膠)の使い方と効果 ・「きわづき」とぼかし ・花模様の表現 ・夜の月を描く ・質感の変化 ・「レジンドーサ」の使い方と効果 ・「マスキングリキッド」の使い方と効果 ・各種白抜き画材の比較 ・金泥と箔について ・色鉛筆とアクリルについて ・刷毛を使う ・スポンジと海綿を使う ・スタンピングのいろいろ ・応用技法:山の民家を描く ・参考作品 ねぎし・かいちろう 1944年、長野県小布施町生まれ。 1970年、日本画家・佐藤紫雲に師事。85に遊墨会、2002年には現代日墨画協会設立。2008年より上野松坂屋にて個展開催。 著書:『墨の美に学ぶ水墨画』『根岸嘉一郎 墨の響き』(日貿出版社)他 現在:現代水墨画協会理事長・遊墨会主宰・現代日墨画協会会長。
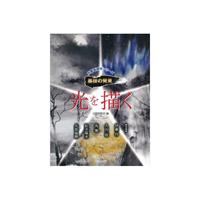
著者:日貿出版社 サブタイトル/水墨画競作シリーズ ジャンル:水墨技法B 体裁/A4変・111頁 現在第一線で活躍中の人気画家が指導する好評の水墨画技法シリーズ第9弾。 伝統的な水墨画の世界では、写実的な光そのものの表現はほとんど見られないが、 現代の水墨画の表現と作品づくりにおいて、「光」は最も重要なテーマの一つとなっている。 本書では、伊藤昌、久山一枝、馬艶、松井陽水、矢形嵐酔の五画人が、現代人の感覚で、 朝日、夕日、木漏れ日、窓から差し込む光、月光、オーロラ、街灯り、炎、花火など、 風景の中の様々な光の表現に取り組み、作品づくりのテクニックとコツを、 豊富な作例とプロセス写真で詳解した。 他に、呉一騏、藤原六間堂の光をテーマとした作品も収録。 ●描法執筆者略歴 伊藤 昌(いとう・しょう) 1967年、宮城県石巻市生まれ。上智大学文学部英文学科卒業。1992年以来、毎年各地で個展を開催。 2001年にはスペイン・マドリッドの個展で好評を博す。 著書:『水墨画 青春彷徨』(秀作社)、『筆ペンイラスト練習帖』(ブティック社)、『花鳥画レッスン』(日貿出版社) 現在:S会主宰、全国水墨画美術協会評議員、総合水墨画展委嘱審査員、全日本水墨作家連同人、他。 久山一枝(くやま・かずえ) 静岡県出身。1967年、東京芸術大学工芸科卒業。1969年、同大学院彫金科修了。岩上青稜氏に水墨画を学ぶ。 1994年、日本クラフト展にて日本クラフト賞受賞。 著書:『尾瀬の四季』、『水墨で描く風景画』、『特殊技法で学ぶ水墨画』(以上、日貿出版社)、他。 現在:新水墨画協会主宰。毎年「日本の美しい自然」展を開催。朝日カルチャーセンター朝日JTB・交流文化塾、 読売日本テレビ文化センター京葉、池袋西武コミュニティ・カレッジ各講師、他。 馬 艶(ま・えん) 1967年、北京生まれ。北京国立中央美術学院を卒業。水墨画、油絵、芸術批評を専攻、油絵と中国画を学ぶ。 2006年より馬驍水墨画会所属「艶墨会」主宰。ホテル椿山荘アートギャラリー・銀座鳩居堂他、個展多数。 著書:『水墨画 黄金の法則』(日貿出版社) 現在:艶墨会主宰、馬驍水墨画会副代表、馬驍水墨画会(銀座教室)講師、日本美術家連盟会員、他。 松井陽水(まつい・ようすい) 岡山県津山市生まれ。多摩芸術学園(現・多摩美術大学)卒業。 文部大臣賞、東京セントラル美術館賞、芸術文化賞など受賞。「趣味の水墨画」(月刊水墨画)連載。 著書:『初歩から学ぶ水墨風景画』(日貿出版社) 現在:日本墨画協会理事長、現代墨画陽水会主宰、全日本水墨作家連同人、一般社団法人日本画府理事、他。 矢形嵐酔(やかた・らんすい) 幼少の頃より書道を学び、公益社団法人大日本書芸院にて一般書道で師範を取得。その後水墨画を橋本鉱酔氏に学ぶ。 カナダ・ブリティッシュコロンビア州政府より招かれ、親善大使としてバンクーバーで水墨画指導。 全国水墨画美術協会作家展等で外務大臣賞をはじめ受賞歴多数。英国ロンドン、仏パリでの巡回個展。 現在:英国ロンドン国際中国画家協会招待、国際中国書法国画家協会本部代表理事、中国遼寧省鞍山市美術家協会理事、全国水墨画美術協会評議員、 国際書画連盟理事審査員、中国蘇州画院無鑑査、中国蘇州画院花鳥画家研究会特別参事、公益社団法人大日本書芸院審査会員、他。
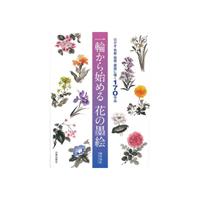
著者:岡村 南紅 サブタイトル/はがき・色紙・短冊・扇面に描く170作品 ジャンル:水墨技法A 体裁/B5変・127頁 一輪の花から、全ての花の墨絵の世界が広がる。 はがきを中心に可憐な花姿を、定評ある流麗な筆致で描き上げた入門者のための書。 代表的な花には詳細な描法解説を加えるとともに、文章や俳句も添えて四季の花170種を紹介。 ●主な内容 序章:花の墨絵入門 用具について/筆の整え方と運筆の基本/葉の描き方/枝・蔓の描き方/花弁の描き方/花の色は墨を加えて描く 【身近な花を描こう1】椿/【身近な花を描こう2】チューリップ/【身近な花を描こう3】桔梗 第一章:春 菜の花・片栗の花・春蘭・山桜・アネモネ・苧環・乙女椿・アヤメ・クレマチス・辛夷・パンジー・白木蓮・沈丁花・海棠・紫蘭・シクラメン・躑躅・猫柳・スイートピー・水芭蕉・ラナンキュラス・八重桜・山吹・蓮華草 紫木蓮を描く/薊を描く/藤を描く 椿・牡丹・薔薇・菜の花・紫露草・チューリップ・桜・君子蘭・アイリス・梅・タンポポ・ハナミズキ・髭撫子・菫・ヒヤシンス・木瓜・レンギョウ・ポピー 第二章:夏 ランタナ・百日紅・凌霄花・ダリア・カーネーション・ガーベラ・ゼラニウム・箱根ウツギ・ナスタチウム・バイモユリ・どくだみ草・ホテイアオイ・芙蓉・向日葵・蓮の花・カラー・額紫陽花・孔雀サボテン・夾竹桃・石楠花・睡蓮 鬼百合を描く/花菖蒲を描く 大待宵草・アマリリス・鹿子百合・ギボウシ・月下美人・キスゲ・梔子・射干・透かし百合・泰山木・ダチュラ・合歓の花・鉄砲百合・矢車菊・蛍袋・ハイビスカス・時計草・アンスリウム・ゼラニウム・山百合・クルクマ・グロリオサ・グラジオラス・石楠花 第三章:秋 コルチカム・秋明菊・桔梗・露草・萩・菊・大毛蓼・カンナ・女郎花・金木犀・小海老草・サフラン・サルビア・秋海棠・野ボタン・撫子・紫苑 朝顔を描く/葛を描く カクトラノオ・アナナス・オシロイバナ・菊・ナンバンギセル・コスモス・鶏頭・芒・鳳仙花・松虫草・ホトトギス・萩・リンドウ・木槿・露草・チランドシア・蝦夷リンドウ・桔梗・彼岸花 第四章:冬 茶の花・シンビジューム・デルフィニウム・山茶花・ストレリチア・フクシャ・ラッパ水仙 水仙を描く/石蕗を描く クリスマスローズ・福寿草・カトレア・ジャコバサボテン・寒緋桜・フリージア・胡蝶蘭・ポインセチア ●おかむら・なんこう 福岡県小倉市(現・北九州市小倉北区)に生まれる。斉藤南北先生に師事し水墨画に出会う。 現在、西日本墨技学院院長及び南北墨画会会長、全国水墨画研究会理事長を務める。 【主な著書】 『四時・花の墨絵』『続四時・花の墨絵』『暮らしの中の花の墨絵』『スケッチから描く水墨画』『花一輪』『季節の画帖』『四季の墨絵・花の墨絵』(日貿出版社) 共著:『墨技の発見花を描く(春・夏篇)』『墨技の発見花を描く(秋・冬篇)』『調墨と運筆を極める』(日貿出版社)
著者:全日本水墨作 サブタイトル/基本から応用まで ジャンル:水墨技法B 体裁/A4変・111頁 現代水墨画界で活躍中の伊藤昌、塩澤玉聖、沈和年、千野曜生、藤﨑千雲、松井陽水、山田大作の7画人による構図レッスン。 実際の作例を挙げ、それぞれにどのような意図をもって構図を決めているかをわかりやすく図解した実践的な内容になっています。また、巻末には「私の好きな名画」のコーナーを設け、等伯や応挙などの名画を紹介。構図を学んだ上での鑑賞のポイントが分かり、実作に役立ちます。 ●ぜんにほんすいぼくさっかれん 「水墨画の未来を見据え、伝統を踏まえつつも多様化する作家それぞれの水墨表現を尊重し、後世に残すべき芸術分野としての水墨画壇を目指す(設立趣旨を要約)」2017年発足の組織。本書はその発起人の中から、7画人の執筆によりまとめられた。
著者:日貿出版社 サブタイトル/水墨画競作シリーズ ジャンル:水墨技法B 体裁/A4変・111頁 「付立法」とは、線を用いずに墨や色で筆勢を生かして描く水墨画の基本描法です。草花の表現においては、濃中淡の諧調が一筆で表現でき、余白と調和した透明感のある画面を生み出すことができます。本書ではこの付立の描法を岡村南紅、伊藤昌、矢形嵐酔が指導するとともに、大月紅石、松井陽水、新倉章子の作品でその魅力に迫ります。 ●目次 没骨法から付立法へ-その技の魅力 岡村南紅 季節の花々で運筆の基本を学ぶ 付立画セレクション1 大月紅石 伊藤昌 省筆の技で「生き物」をとらえる 付立画セレクション2 松井陽水 矢形嵐酔 大胆な筆墨技法で現代を描く
著者:日貿出版社 サブタイトル/水墨画競作シリーズ ジャンル:水墨技法B 体裁/A4変・111頁 水墨画においても風景を描けば人の住むところ必ずや建物があり、それらが主題や添景として重要な役割を果たしています。中でも神社や寺院は日本全国に見られ、人々を引き付ける名勝地もあり、また古い街道から高層ビルまで、いたるところに印象的な街並みがあります。日本の風景はまさに画題の宝庫といえましょう。 本書は、久山一枝、伊藤昌、根岸嘉一郎による寺社や街並み、城や橋などの描法解説と作品、また松井陽水と藤原六間堂による日本や海外の建物の作品を収録して、水墨画による建物の創作のポイントを解説しました。なお巻末には、建物をテーマとして描いている作家・愛好家の中から執筆陣と編集部がセレクトし、その作品を収録しました。